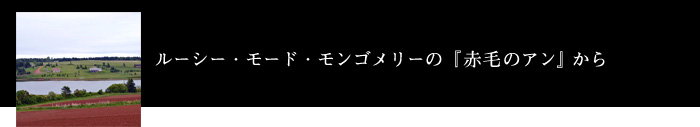
ルーシー・モード・モンゴメリーの「赤毛のアン」は1904年、執筆が始まり、1908年に出版された。1900年と言うと日本では、明治33年で、封建時代そのものと言える頃であった。すなわち、自由・平等とは程遠い時代であった。
モンゴメリーは1894年カナダのプリンスエドワード島で生まれた。彼女が2歳の時、母親が結核で亡くなっている。母方の祖母に育てられた。小学校はキャベンディシュ(アヴォンリー村のモデル)の学校で過ごした。一時期カナダ本土プリンスアルバートで、再婚した父親と義母とも暮らしたこともあるが、1891年、17歳の時プリンスエドワード島に戻り、シャーロットタウンの教員養成学校を卒業し、プリンスエドワード島のビデフォードで1年教員をした。その後1年大学に通い、文学の勉強をしている。16歳の時から、雑誌社に短編小説を投稿しており、文学熱は高かった青春時代を過ごしている。
「赤毛のアン」を書き出した1904年は、モンゴメリー30歳の時であるが、この前年に後に結婚した牧師ユーアン・マクドナルドがキャベンディシュ教会に赴任している。この時代モンゴメリーは教会ではオルガン奏者をしていたそうである。1906年、ユーアンと婚約。実際に二人が結婚したのは1911年である。
簡単ではあるが、モンゴメリーの略歴を記した。ここでわかることは、モンゴメリー自身は、孤児ではないが、母親がいなく、祖母に育てられ、この経歴は、アンと一部重なる。また教師をした経験は、小説の中で、いろんなタイプの子どもたちを描くのに役立っている、と感じる。後で述べるが、新任牧師のアラン夫妻が登場する辺りから、アンから見たアラン夫人への憧れを通して、キリスト教関係の記述が多くなる。
高校時代、旺文社の雑誌「高校時代」で、感動した外国小説の特集を読んだことがある。私の50年ほど前の記憶では、ランキングが載っており、男子の1番は、トーマス・マンの「トニオ・クレーゲル」かヘルマン・ヘッセの「デミアン」のどちらかだった、と思う。女子は、圧倒的に「赤毛のアン」であった。日本での「赤毛のアン」の翻訳・出版は1952年である。村岡花子が翻訳者であった。彼女は1893年生まれで、クリスチャンの家庭で育ち、幼児洗礼を受けた。父親がすごく変わっていて、1904年にカナダ人宣教師が設立した東洋英和女学校に女中兼生徒として花子を預けてしまった。花子は学校・私生活でカナダ人宣教師と英語でコミュニュケーションをとる生活を余儀なくされた。東洋英和女学校を卒業後、山梨英和女学校で英語の教師になり、その後1917年にキリスト教関係の本を取り扱う教文館に雑誌の編集者として就職した。日米戦争が激しくなる最中、1939年カナダ人宣教師が、カナダに帰る時、一冊の本「 Anne of Green Gables 」を花子に託した。花子は戦争中の灯火管制の厳しい中で、その本を必死に翻訳した。それが1952年「赤毛のアン」と言うタイトルで出版された訳である。
「赤毛のアン」の日本での出版が1952年と言うことは、この時代にこの本を読む年齢層は少なくとも当時10歳〜15歳である。すなわち1937年(昭和12年)以降の人と言うことになる。終戦時は8歳である。昭和20年の敗戦、昭和21年11月3日日本国憲法の公布、昭和22年5月3日の施行によって、従来の価値観は180度変わった。「国民主権」、「基本的人権の尊重」、「平和主義」が日本国憲法の3大要素とされる。第24条は、家庭生活における個人の尊厳と両性の本質的平等について定める。旧憲法下では、女性の法的地位は男性より劣るものとされていた。私は昭和23年生まれであるが、子どもの時代女性蔑視の名残を多く見た。とは言え建前は男女平等の時代となった。
「赤毛のアン」の主人公アンは、想像力豊かなかわいい女の子ではあるが、学校では男子に負けないパワーを持つ。成績もよく、失敗を重ねながらも、どんなことにも挑戦する。ここには、女だからダメである、女のくせして、とする日本の昔あった風潮は微塵もない。
話は前後するが、「赤毛のアン」の概略ストーリーをまとめておく。話は、プリンスエドワード島のアヴォンリー村(架空の地であるが、小説に表記されている他の地名、その他からモンゴメリーの育ったキャベンディシュであることがわかる)に住む年老いたマシューとマリラの兄妹(二人とも独身)が、畑仕事を手伝ってくれる男の子どもを(孤児)引き取ることを、慈善事業をしているスペンサー夫人に頼む。しかし手違いで、男の子ではなく、女の子が用意されてしまった。マシューは、その女の子「アン」の魅力に心動かされ、アンと一緒にいたい気持ちになってしまう。妹マリラは、女の子なんてとんでもない。アンを返すため、スペンサー夫人のところに、アンを連れて出かける。
マリラはアンのおしゃべりに辟易しながらも、彼女の身の上話を聞いてしまう。マリラは無愛想な女性ではあるが、善人である。アンが孤児であることは、彼女の責任ではないことを理解する。マリラはスペンサー夫人にアンを返そうとするが、丁度その時アンを欲しいと言うブリュエットが現れる。そのブリュエットは、アンを自分の家の子守役と小間使いの為に欲しい訳である。マリラは、兄のマシューはアンを育てたがっていたし、今この状態でアンをブリュエットに渡すことは、良心の呵責を感じるので、再び、アンを家に連れ戻してしまう。そしてアンを養女にする決心をマシューに話す。アンは基本的にはマシューの意向を尊重する女性である。ここまでが、1章から6章までである。マシューとマリラの兄妹は、自分たちの老後を支えてくれることを望み、男の子を欲しがったが、アンに会って、考えが変わった。いや、生き方が変わったと言ってもよい。
3章「だが、そのう、あの子を引きとるのは、やっぱり難しいかのう」
「当たり前ですよ。あの子が私たちの何の役に立つんですか」
「でもなあ、わしらが、あの子の役に立つかもしれないないよ」
突然、マシューは思いがけないことを言った(集英社文庫、松本侑子訳「赤毛のアン」より、以下同じ)。まさしく、コペルニクス的転換。価値観が180度転換した。
信心深いマシューには、
『人にしてもらいたいと思うことを、人にもしなさい。』ルカによる福音書 6章 31節
『あなたがたの父が憐れみ深いように、あなたがたも憐れみ深い者となりなさい。』同6章 36節、これらの聖句が思い浮かんだのであろうか。
土壇場で、マシューは、生活の手段の改善より、孤児に寄り添い、支える道を考えた。
6章「あれこれ考えるうちに、引き取るのが、私の務めじゃないかと思えてきたのですよ。子育ての経験はないし、ましてや女の子だから、私も何か間違いをするかもしれないけど、できるだけのことはしますよ。マシュー、私は、あの子をひきとってもいいですよ」
「そうさな、おまえはきっと分かってくれると思っていたよ、マリラ。何しろあの子は面白い子だからな」
マリラは、無愛想な女性だが、子育ての経験がないこと、特に女の子の育て方がわからいので、アンを引き取ることに積極的でなかったことがわかる。しかし、彼女もマシューと同じく慈悲心の持ち主であった。
マシューとマリラは、老後の畑仕事の負担を軽減したいと言う願いより、今この現実(アンの存在)を直視し、それは神からの問いかけと理解し(無意識ではあるが)、人生の新しい意味を見出した、と言える。これこそミッションの発見ないし自覚と言えるのではないであろうか。
アンは、カスパート家に来た時11歳であったが、空想に耽ることが好きな女の子であるが、一方では様々なことに挑戦し、事件ないし失敗の連続を仕出かす。読者はアンの失敗が面白くて、ますますアンが好きになる。
第9章、リンド婦人に容姿をけなされたアンは、罵詈雑言をリンド夫人に浴びせる。
第10章、リンド婦人に謝ることをマシューに促されたアンは、芝居かかった侘びを入れるが、反対にリンド婦人に気に入られてしまう。
第14章、ピクニックに行きたくて、マリラのブローチがなくなったのは、自分が落としたと嘘の告白をしてしまう。
第15章、ニンジンと呼んでアンをからかったギルバートを石板で頭を叩き、石板を真っ二つに割ってしまう。この事件を契機にギルバートの隣に座らせられたアンは学校に行かなくなる。「アンはギルバートを憎めば憎むほど、それと同じ激しさで、ダイアナを小さな胸の底から、全身全霊をかけて愛した。アンは愛情も憎悪も同じように激しいのだった」
第16章、ギルバートの事件と並んで極めつけの失敗である。木苺水とスグリの果実酒を取り違え、こともあろうか腹心の友ダイアナを酔っぱらせてしまう。ダイアナの母は、カンカンに怒り、アンを出入り禁止としてしまう。
第18章、ダイアナの妹のミニー・メイがクループという病気になってしまう。親たちは留守で、心配のあまり、ダイアナはアンに助けを求める。アンは孤児院に入る前、ハモンドさん一家で子守役として生活していた。そこには3組の双子がおり、その子たちが順繰りにクループにかかり、その看病の仕方をアンは知っていた。アンは果敢に看病し、医者が到着する前に、病気の峠を越させた。後で医者は言った。「カスパートさんの家のあの赤毛の女の子ですが、あんなに賢い子はいませんよ。あの子がお子さんの命を救ったんですよ。私が着いてからでは、手遅れだったでしょうからな。介抱の腕と言い、急場の冷静な度胸と言い、あの年頃の子にしては、たいしたものですよ。」16章のアンの出入り禁止は当然解除になる。
第19章、老女ミス・バリーが客間のベットで寝ていることを知らなかったので、アンとダイアナは、走ってそのベットに飛び乗り、老女を死ぬほど驚かせた。謝ったアンのユニークさをミス・バリーは見つける。「あの子はまことに面白い。この年になると、そうそう面白い人物にはお目にかかれないもんでね」アンも言う。「ミス・バリーは心の同類だったわ」
第21章、新任のアラン牧師夫妻をカスパート家のお茶に招いた。アンがケーキを焼いたのだが、砂糖と痛め止めの塗り薬を間違えてケーキに入れてしまった。マリラが砂糖の空き瓶に痛め止めの塗り薬を入れたことをアンに言わなかった為に起きた事故であった。不運なことにアンは風を引いており、鼻詰まりで匂いが確認できなかった。
マリラは言った。「あんたみたいな失敗の天才は、みたことないよ、アン」
「ええ、分かっているわ」「でも、マリラ、私にも、一つは励みになることがあって、同じ失敗は二度としないのよ」「まあ、マリラ、一人の人間がする過ちには、限りがあるはずだわ。最後までやってしまえば、それで私の失敗も終わりよ。そう思うと、気が楽になるわ」
第23章、「できるものならやってみよ」の遊び、これをやってみよと挑まれたら、その人は受けなければならない遊びで、アンは屋根の棟の上を歩いた。しかし落っこちて、足首が折れ、7週間学校を休み、ベットにいた。代わる代わる見舞いに来る友達とのおしゃべりは絶好調。マリラが言った。「バリー家の屋根から転がり落ちても、あんたの舌は、かすり傷一つおわなかったってことだ」
第27章、行商人から毛染め薬を買ったアンは、黒く染めるはずが、緑色になってしまった。一週間外には出ないで髪を洗い続けたが、緑色は落ちない。そこで髪の毛を刈り上げてしまった。学校でジョージ・パイに「まるで案山子にそっくりね」とアンは言われてしまうが、彼女は以前のようには怒らなかった。
第28章、物語クラブで、アンは百合の乙女役を演じ、ボートで流される役をする。ところがボートに水が漏れ出してしまう。かろうじて橋桁につかまり、助けを待つが、そこへ偶然ギルバートがボートで通りかかる。アンはギルバートに助けられる。2年前のニンジン事件からアンはギルバートを避けていたので、ギルバートはアンと口を利いた事がない。ギルバートは友だちになるようアンに言うが、アンは断ってしまう。
第30章、ステイシー先生が、アンの留守の時、カスパート家を訪ねて来た。先生が何のために来たのかわからないアンは、授業中先生の話を聞かず、小説「ベン・ハー」を読んでいたことが先生に見つかり、アンは叱られた。そのことを家に告げに来たとアンは勘違いした。先生は、クィーン学院への受験の意思がマシューとマリラにあるのかを聞きに来たのであった。「あなたを引きとったとき、マシューと決めたんだよ。できるだけのことをしてやって、いい教育も受けさせようってね。女の子は、たとえその必要があろうとなかろうと、生活費ぐらい自分でかせげる能力をみにつけていた方がいいからね。(中略)アン、あなたが行きたいのなら、クィーン学院の受験クラスに入っていいだよ」この発想は日本より50年早かったような気がする。
長々と「赤毛のアン」の事件ないしアンの失敗を見てきた。これらの事件、失敗はアンの無邪気さから引き起こされたものばかりで、読者は笑いと共にアンを愛さずにはおれない気持ちにさせられる。
私が「赤毛のアン」を読んだのは、遅く、64歳の時であった。2012年5月30日〜6月5日に、妻と義母の三人でプリンスエドワード島へのツアーに参加した。その時の行きの飛行機の中で読んだのである。妻は、「赤毛のアン」の正真正銘のフアンで、1年に1度は、「赤毛のアン」を繙いていた。心落ち着けたいのか、過ぎ去った青春の追憶に思いを寄せるのか、本当によく読んでいた。私は、「赤毛のアン」は女の子が読む小説という固定観念に囚われたせいか、読む機会がなかった。しかし、滑り込みセーフで、プリンスエドワード島に着く前に、ビールを飲みながら、読了した。
いやー、面白いと感じると同時に、これはキリスト教の匂いがプンプンする本だと感じた。マシュー、マリラは熱心なクリスチャンとして描かれているし(第25章、「実は、カスパート家では、買物はウィリアム・ブレアの店が行きつけだった。それは、長老派教会に通い、保守党に投票すると同じように、一家の良心にかかわる問題といってもよかった。」)、アンの信仰も子どものころから少女になるに従い、成長する。小説の中から、それらの事例を考えてみたい。
第7章、マリラは、アンに寝る前のお祈りを促すが、アンは、「私、お祈りはしないの」と言った。また、自分の赤毛は、神様のせいだし、夜はくたくたで(子守のため)、お祈りどころじゃなかった、と言う。マリラがお祈りの仕方を教えると、アンは言う。「どうしてお祈りの時にはひざまずくの?私なら、心からお祈りしたくなったら、たった一人で、広い原っぱか、深い森に出かけて、空を仰ぎ見るわ。どこまでも、どこまでも高く、高く、その青い色に果てがないくらい美しい青空を見上げるの。そうすれば、心にお祈り感じるでしょうよ。はい、ひざまずきました。それから何というの」アンの言っていることは、正しいような、間違っているような、微妙な気がする。祈りが、神様との交流とすれば、形に囚われるのは、間違いである。しかし、日常生活の中で根付く習慣となるためには、一つの形がいることも事実である。本当に心だけの問題であるなら、教会に行かなくてもよいとも言える。反対に、教会に行っても寝ているだけであったら、これまた教会に行くことは、無駄である。しかし、日本キリスト教団信仰告白を素直に読む限り、「教会は主キリストの体にして、恵みにより 召されたる者の集いで」あり、「聖なる公同の教会、聖徒の交わり」を信じ、習慣的クリスチャンではなく、熱心なクリスチャンになるためには、教会へ行くこと、祈ることの形も必須と言えるのであろう。
第8章、アンは1枚のキリストと子どもたちの絵を見て、神様を描いた絵はみな神様が哀しそうな顔をしており、子どもたちは、それを見て神様を怖がってしまう、と感じたことを言う。マリラは言う。「アン、そんなことを言うものではありません。罰あたりです、まったくもって不届きです」「神様のことを馴れ馴れしく言うのは感心しません」マリラにとっては、キリストの容姿を云々言うことは、憚られることであった。昔の映画、チャールストン・ヘストン主演の「ベン・ハー」を思い出す。キリストが通ったことを光と陰で示すが、姿は画面に出てこなかった。やはり、恐れ多いことであったのであろう。第7章、第8章は、宗教教育をあまり受けなかったが、神様に対する素朴な心を持つアンを、熱心な大人の信者であるマリラとの対比において述べる。
第10章、アンは、ふいにマリラにすり寄り、小さな手を、老いたマリラの硬い掌にすべり込ませた。「ああ、マリラ、私とても幸せ。今なら、すぐにでも。やすやすとお祈りできそうよ」マリラは一瞬、母親らしいときめきを感じた。「いい子でいれば、いつも幸せなんですよ、アン。そうすれば、お祈りの言葉を唱えるのも難しくありません」「お祈りの言葉を唱えることと、祈ることは、厳密には違うわ」アンは瞑想に耽りながら言った。
アンは、グリーン・ゲイブルで生活できるようになり、優しい気持ちが甦る。それは、マリラにも伝染し、彼女の眠っていた母性をくすぐり、さらに祈りの根本にも触れる成長の根が見えだした。第11章は、アンが日曜学校(教会)に行くことが書かれ、その後いろんな事件や失敗談が書かれるが、基本的には学校生活と日曜学校の生活が1年続く。
第21章は、アヴォンリーの教会の牧師の交代について書かれている。アンとマシューが牧師の品定めをする話や、若い新任のアラン牧師夫妻が理想的に書かれ、当時の作者モンゴメリーの夢が書かれているようでもあり、とても面白い。「マシュー、私は、アランさんが牧師に決まって、嬉しいわ。お説教は面白いし、それに、習慣だからお祈りするんじゃなくて、心からなさるもの。」またアラン牧師夫人を崇拝するアンはこうも言う。「夫人は、どんなことだって、それはすてきに話すの。信仰がこんなに楽しいものだとは、知らなかったわ。信仰って、陰気なものだと思っていたけど、アラン夫人は違うの。アラン夫人のようになれるのなら、私もクリスチャンになりたいわ。」
第22章ではさらにエスカレートする。「大きくなったら、牧師さんの奥さんになりたいわ、マリラ。」アラン夫人に日曜学校の合唱隊に入るよう言われ、アンは有頂天になると同時彼女に心を開く。この時期、学校の先生もステイシーと言う女性教師に変わり、アラン夫人とこの教師がアンの成長を見守ることとなる。
さらに3年が経ち、第31章、「私も男だったら、牧師になりたいわ。」「でも、マリラやマシュー、それにアラン夫人、ステイシー先生のようなすばらしい大人と一緒なら、私も立派な大人になれると思うわ。」第32章、アンは、クィーン学院受験で、1番での合格が判明した。「そして夜、アンは自分の部屋に入り、穏やかな気持ちで窓辺にひざまずいた。開けはなった窓から、月の光が煌々と射しこみ、アンを照らしていた。アンは、心の底から湧き上がる感謝と抱負をこめて、祈りの言葉をつぶやいた。過ぎ去りし日々への感謝と、未来への願いがこめられた祈りだった。」『そして、いつも、あらゆることについて、わたしたちの主イエス・キリストの名により、父である神に感謝しなさい。』エフェソの信徒への手紙5章20節 『だから、こう祈りなさい。天におられるわたしたちの父よ、御名が崇められますように。御国が来ますように。御心が行われますように、天におけるように地の上にも。』マタイによる福音書6章9節、10節
子どもの頃、お祈りしなさい、と言われても、何を祈ればよいか、よくわからなかった。よくテストで良い点がとれますように、という願い事を祈ったことを記憶している。感謝、しかも神に対する感謝が、祈りの一つの大きな柱であることを知るには、時間がかかった。アンは15歳にして、祈りを会得したようである。彼女の成長を心から喜びます。
赤毛のアン」は、主人公アンの11歳から16歳までの出来事を書いた小説で、孤児であった彼女が、アヴォンリーという架空の村に住む年老いたマシューとマリラの兄妹に引き取られ、個性を発揮していく過程を描いた一つの「成功物語」と捉えるのが一般的である。このことは、私も何ら否定しないが、64歳で初めてこの小説を読んだ者としては、同年代のマシューとマリラの魅力に心打たれた。そのことを少しまとめておきたい。
マシューと言う名前は、聖書のマタイの英語読みであることは、明らかである。マシューは、最初から最後までアンの良き理解者で、寡黙であるが、神を信じ、仕事に精を出す素敵な老人として描かれる。
第25章、マシューは、アンの着るバスリーフ(当時流行の袖の部分にふくらみをつけたドレス)の生地を買いに店に行くが、うまく店員に説明できず、熊手、砂糖など関係ないものを買ってしまう。結局、生地を買うこととバスリーフに仕立てることをリンド婦人に頼む。リンド婦人曰く、「でも、そのことにマシューが気がついたとはねえ!(他の子はバスリーフを着ているが、アンはマリラの作った質素な服を着ている)あの男も、60年以上も眠っていたみたいなもんだが、やっと目が覚めたんだね。」マシューは、アンのためなら、何でもする暖かい心を持った老人なのである。
第34章、「あの子は賢くて、きれいだ。それに、愛情深い子だ。これが何よりもいいことだ。神様があの子をわしらに授けてくださっただな。スペンサー夫人も、まったく運のいい手違いをしてくれたものだ。これが単なる運の話ならばだがな。しかし、これは運の善し悪しなんてものではない、神様の思召しだ。思うに、全能の神は、わしらにはあの子が必要だとご覧になったんだよ」『あなたがたがわたしを選んだのではない。わたしがあなたがたを選んだ。』ヨハネによる福音書 15章16節
第36章、「もし私が、マシューが最初に手配したとおり、男のだったら」アンは悲しそうに言った。「今ごろはたくさん手伝ってあげて、いくらでも仕事を楽にしてあげたのに。だから、私が男の子だったらよかったのにって思うわ」「そうさな、でもわしは、1ダースの男の子よりも、アンの方がいいよ」マシューのアンに対する絶対的な信頼に心が打たれる。
マリラの名前も聖書マリアの変形である。アンに厳しく接するが、それは彼女の子どもを育てることの責任感のなせる業である。また、飾ることを極端に嫌い(第3章、「部屋全体が、言い表せないくらい厳しく、アンは骨のずいまでふるえ上がった。」)、愛情表現も稚拙である。アンの失敗に教訓を垂れ、諭すのが、大人の義務と考えている。第10章で見たように、アンの無邪気な心・態度はマリラのさび付き始めた心を溶かし始め、それは次第に心の深い部分に達する。第30章、「この灰色の目をしたやせた少女を、いっそう深く激しく愛するようになっていた。愛しすぎるあまり、アンを甘やかしやしないかと不安になるほどだった。マリラはアンを一途に愛していたので、生身の人間をこんなにも強く愛するなんて、神への冒涜ではないかと気がとがめた。そこで、アンをさほど大切に思っていないかのように、冷淡に厳しく当たることで、無意識に罪滅ぼしをしているかもしれなかった。」
第31章、マリラに人を愛することを教えてくれた小さな子どもは、いつもまにか跡形もなく消えてしまい、その代わりに、目の前には、すらりと背が高く、真剣な眼差しをした15歳の少女が、思索的な顔つきをして、小さな頭を誇らしげにそらして立っているのだ。マリラは思わず泣いてしまった。「アンのことを考えていたのですよ。いつのまにかあんなに立派な娘になって。来年の冬は、もうこの家にいないんですよ。あの子がいなくなったら、どんなに寂しいでしょうねえ」
第37章、突然であるが、マシューは死んでしまう。「私にとってマシューは、いつも心根の優しい、いい兄さんだった。ども、これも神様のおとりはからいだからね」「私は頑固者で、あんたに厳しかったと我ながら思うよ。だからといって、マシューほどあなたを愛していないだなんて、思わないでおくれ。今なら言えそうだから、言うよ。自分の気持ちを口にするのはどうも苦手だけど、こういう時なら、言えそうだかね。私はあんたのことを、血と肉を分けた実の娘のように愛しているんだよ。グリーン・ゲイブルズに来たときからずっと、あんたは私の歓びであり、心の慰めだったんだよ」(この第37章は、村岡花子訳の新潮文庫版では、2008年の改訂版までは、極端に省略されており、これ以前の版で読んだ人は、このマリラの告白は読んでない)村岡花子も、年老いたマリラが直接アンに向かって、あなたが好きである、と言う表現は、似つかわしくないと考えたのであろうか。日本人は愛情表現が下手と言われる由縁である。
第38章、アンは大学の奨学金を獲得し、大学に進学してグリーン・ゲイブルズを離れる予定であった。しかし、マリラの目が悪くなり、一人で生活するのが困難になりかかった。アンは重要な決断をする。大学進学をあきらめ、教師をしながら、マリラとグリーン・ゲイブルズで生活をすることを選ぶ。「マリラ、この一週間と言うもの、ずっと考えていたのよ。私はここで生きることに最善を尽くすわ。そうすれば、いつかきっと、最大の収穫が自分に返ってくると思うの。クィーン学院を出た時は、私の未来は。まっすぐな一本道のように目の前にのびていたの。人生の節目節目となるような出来事も、道に沿って一里塚のように見わたせたわ。でも、今その道は、曲がり角に来たのよ。曲がったむこうに、何があるか分からないけど、きっとすばらしい世界があるって信じているわ。」
前述したように、マシューとマリラは、アンを育てることを神からのミッションとして捉えた。今度はアンが、マリラとグリーン・ゲイブルズで生活することをミッションとして捉えたわけである。マシューとマリラは、人生は神から与えられた恩寵として、神に感謝して生活した。アンは、マシューとマリラに育てられ、同じく神の恩寵を感じる人として成長した。彼女にとって、人生そのものがミッションと言えるのであろう。 「赤毛のアン」は次のような文で全章を閉じる。「『神は天に在り、この世はすべてよし』」アンはそっとつぶやいた。
終わり
Merryy Christmas
皆様のうえに、愛にあふれた豊かなクリスマスが与えられますよう、お祈りしております。
Wishing your family peace and love at Christmas and always.
★Next (詳しいメニューは左メニューからご自由にお選びください。)